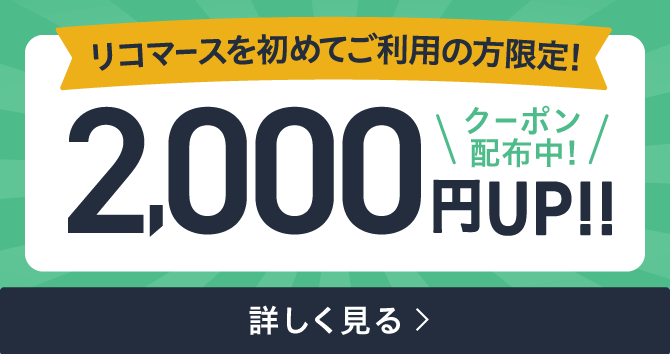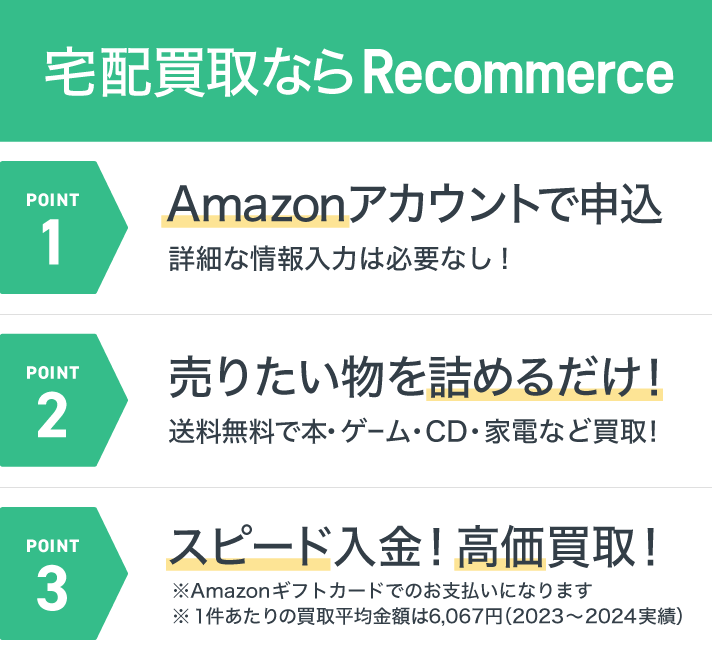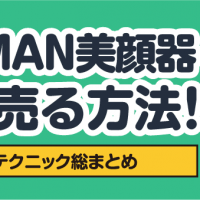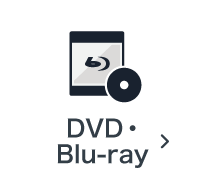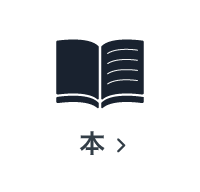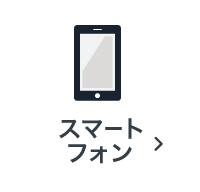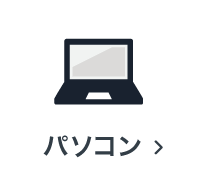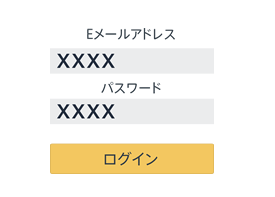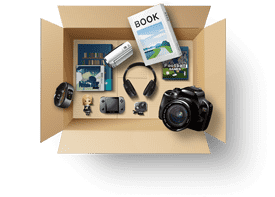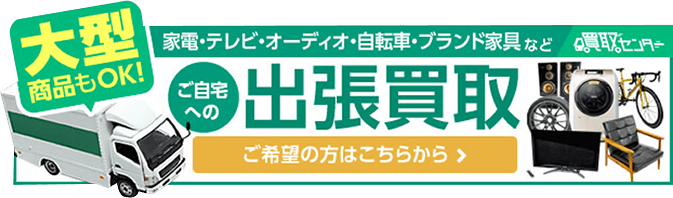買取のコツ
本人確認方法の選択肢についてご紹介します!
近年、インターネットやフリマアプリの普及により、不要になった物を手軽に売却できるようになりました。
しかし、その一方で、盗品や不正な商品が流通するリスクも高まっています。
このような状況の中、古物商法では、古物商に対して本人確認義務を課すことで、犯罪の防止と被害の迅速な回復を図っています。
本記事では、古物商の本人確認義務について、その目的や方法、注意点についてご紹介します。
古物商にとって、本人確認義務は非常に重要な責務の一つです。
スムーズな取引のためにも、本人確認義務についてしっかりと理解しましょう。
□買取における本人確認について
古物商が中古品の買取りや貸し出し、またはそれらの委託を受ける際には、原則として相手方の本人確認を行う義務があります。
これは身分証明書などを用いて行います。
一方で、古物を売却する際には本人確認の必要はありません。
本人確認義務が課せられている理由は、古物商法の目的にあります。
古物商法は、盗品等の売買防止や速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止と被害の迅速な回復に資することを目的としています。
つまり、本人確認義務により、盗難品などの不正な商品の流通を阻止し、犯罪の抑止力とすることが期待されているのです。
本人確認義務の対象となる取引は、中古品の買取り、貸し出し、委託の3つです。
ただし、買取り価格が1万円未満の場合や、同じ品物を売却した相手から買い取る場合は例外とされています。
しかし、書籍、CD・DVD・BDなどのメディアディスク、ゲームソフト、オートバイ及びその部品については、買取価格に関わらず本人確認義務があるので注意が必要です。
本人確認の方法としては、運転免許証などの身分証明書の提示、家族や勤務先への問い合わせ、住所、氏名、職業、年齢を記載した書類の提出、電子署名などが一般的です。
本人確認を行った際は、確認した内容を古物台帳に記録することも義務付けられています。
□古物商三大義務について
古物商法では、本人確認義務に加えて、古物台帳への取引記録義務と不正品申告義務の3つの義務が課せられています。
これらは「古物商三大義務」と呼ばれ、古物商にとって非常に重要な責務となっています。
まず、古物台帳への取引記録義務では、古物の取引内容を古物台帳に記録し、3年間保管することが求められます。
記録すべき内容は、取引相手の氏名、住所、職業、年齢、本人確認の方法、古物取引内容(品目や数量など)、取引年月日、古物の特徴などです。
古物台帳は、盗難品などの不正な取引が行われた際の警察による捜査に役立つ重要な資料となります。
次に、不正品申告義務では、買取した古物に盗難品などの疑いがある場合、警察に申告することが義務付けられています。
盗難品などの疑いがある場合は、速やかに警察に申告し、捜査に協力する必要があります。
これらの義務を違反した場合、古物商は営業停止処分や古物商許可の取り消し処分を受ける可能性があります。
古物商三大義務は、古物商にとって非常に重要な責務であり、しっかりと遵守していく必要があります。
□対面取引における本人確認方法の選択肢
対面取引における本人確認方法には、大きく分けて4つの選択肢があります。
1: 身分証明書等の提示を受ける方法
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公的な身分証明書を提示してもらい、住所、氏名、職業、年齢を確認します。
最も一般的な方法と言えるでしょう。
2: 相手方の家族等に問い合わせて確認する方法
相手方以外の親兄弟、配偶者、勤務先などに問い合わせて、相手方の身元を確認します。
身分証明書の提示が難しい場合などに有効な方法です。
3: 確認事項を記載・署名させた文書の交付を受ける方法
相手方に、住所、氏名、職業、年齢を記載した書類(買取申込書やお客様カードなど)に署名してもらい、確認します。
書面で残るため、トラブル防止にも役立ちます。
4: タッチペン等を使用して署名させる方法
電子タブレット等の画面に氏名をタッチペン等で署名させ、確認します。
デジタル化が進む中で、利便性の高い方法と言えるでしょう。
これらの方法から、取引の状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
□非対面取引における本人確認方法の選択肢
近年、インターネットを通じた中古品の売買が増加しています。
非対面取引では、対面取引と比べて本人確認が難しいという課題がありますが、いくつかの有効な方法があります。
1: オンライン本人確認サービスを利用する方法
本人確認サービスを利用することで、オンライン上で本人確認を行えます。
手軽で確実な方法と言えるでしょう。
2: 郵送による本人確認書類の提出を求める方法
相手方に、運転免許証などの身分証明書のコピーを郵送してもらいます。
書類が手元に残るため、トラブル防止にも役立ちます。
3: 電話による本人確認を行う方法
相手方に電話をかけ、本人確認を行います。
声を聞くことで、ある程度の本人確認が可能です。
4: 顔認証技術を利用する方法
顔認証技術を利用することで、オンライン上で本人確認を行うことができます。
手軽で確実な方法ですが、技術的な課題もあります。
非対面取引における本人確認は、対面取引と比べて難しい面がありますが、これらの方法を適切に組み合わせることで、確実な本人確認が可能となります。
□買取における本人確認の注意点
古物商法では、本人確認の際にいくつかの注意すべき点があります。
1: 運転免許証などの身分証明書はコピーを取ることが禁止されている
本人確認の際は、原本を確認するようにしましょう。
2: 職業の確認では、「会社員」や「自営業」といった曖昧な表現では不十分
勤め先や屋号までしっかりと確認する必要があります。
3: 住所の確認も重要
住所が正確かどうか確認し、偽造されている可能性がないか注意が必要です。
本人確認を行った際は、確認事項を記載した書類を3年間保管する義務があります。
書類の保管を怠ると、義務違反となる可能性があるので注意しましょう。
最後に、盗難品などの疑いがある場合は、捜査に協力する必要があります。
これらの注意点を踏まえ、適切な本人確認を行うことが求められます。
□まとめ
本記事では、古物商の本人確認義務について、その目的や方法、注意点などを詳しく解説しました。
古物商は、本人確認義務、古物台帳への取引記録義務、不正品申告義務の3つの義務を遵守する必要があります。
これらの義務は、盗難品などの不正な商品の流通を阻止し、犯罪の抑止力とすることを目的としています。
対面取引での本人確認方法としては、身分証明書の提示、家族や勤務先への問い合わせ、確認事項を記載した書類への署名、タッチペン等での署名などがあります。
非対面取引では、オンライン本人確認サービスの利用、郵送による本人確認書類の提出、電話による本人確認、顔認証技術の利用などが有効です。
本人確認の際は、身分証明書のコピー禁止、職業や住所の詳細確認、確認書類の保管、警察への協力など、いくつかの注意点があります。
これらの点に留意し、適切な本人確認を行うことが求められます。
古物商法の義務を遵守し、適切な本人確認を行うことで、盗難品などの不正な取引を防ぎ、安全で信頼される古物取引の実現につながります。